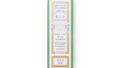お香の老舗、薫玉堂さんのお香、音羽の滝。
公式には、”清水さんの滝つぼに流れ落ちる東山三十六峰に連なる音羽山の湧水。千年以上もとぎれることのない、清らかで涼やかな流れを連想させる薫り。” の説明区。
京都の清水寺にある音羽の滝をイメージした、シリーズの中でも人気のお香。
トラディショナルの中に、爽やかさや華やかさを感じる香り。
薫玉堂というと、音羽の滝というイメージがあるくらい、薫玉堂の中では有名なお香だ。
なので、外れる心配はしていないが、どんな香りかはある程度知っておきたい。
そう思い、口コミを漁るのだが、”爽やか” というワード以外、いまいちそれっぽいワードが出てこない。
とりあえず、薫いてみるのが早そうだ。
火を付けると漂う、トラディショナルですっきりしていて、それでいてしっかりした香り。
あぁ、良い、くどくなく、爽やかさももっていて、ほんのり甘みや華やかさもある、日本人受けする香りだ。
そして確かに、これは言葉にしにくい。
軒並み抽象的なレビューばかりなのも頷ける。
まず、ベースになっているのは、薫玉堂さんの他のお香と同じ、薫玉堂さんらしい芯のあるお香感や華やかさだ。
モダンさもあるが、トラディショナルな馴染みやすさもある、モダンな和のお香感だ。
そして、”滝” というと、水のような透き通るような感じをイメージするかもしれないが、思ったよりも透き通ってはいない。
そもそも音羽の滝というのは、観光名所である清水寺の中にある人口的に作られた滝であり、バシャバシャと水飛沫をあげるような滝ではない。
厳かなお寺の一部なので、ダイレクトに清涼感があったとしたら、それはそれでちょっと違うのだろう。
さて、深掘っていこう。
口コミにある “爽やかさ” を探して煙を優しくパタパタとし、よく嗅いでみると、爽やかな香りが出てきた。
爽やか… マリン系なのだろうか、ミントなのだろうか、そのどれかのような気もするが、どれでもない気もする。
マリン系、というのは自然界に存在する香りではなく、いわばマリンをイメージして人口的に作られた香りだ。
人口香料だとか天然香料だとかの話ではなく、マリン系という香りの系統自体が、人の想像で作られた香りだということだ。
それと同じく、これも滝をイメージを元に、人工的に作られた系統の香りなのだろう。
同じ “水” というところで、このマリン系の香りの爽やかさに通ずるものがある。
決してマリンではないのだが、想像で作り出した爽やかさ、というところで、共通している。
そして、ミントの香りという口コミがあったが、他のお香に比べると、確かに少し清涼感がある。
他のお香を薫いた後に薫くと、確かに少しだがスースーした清涼感があるのがわかる。
ミントそのものの香りは感じないので、ミントというよりメントール感といったほうが、正確だろうか。
清涼感を求めるとちょっと物足りないのだが、他の香り成分を邪魔しない配合になっている。
これがまた、絶妙な塩梅だ。
そんな爽やか系の香りに、なんの花かわからない程度に、花の華やかさや甘さがのっている。
もし私が、何も説明されずお香だけ渡されたら、おそらく「水辺に咲いている青くて清々しい花の香り」と答えるだろう。
そんな複雑な個性と、トラディショナルなお香感が重なり、凄く良いとこでまとまっている。
甘すぎない、すっきりしすぎない、モダンすぎない、古臭すぎない、何とも言葉に出来ない香りだ。
そして唯一無二なのに、人を選ぶような癖もなく、万人受けする香りになっているのが、面白い。
甘すぎるお香は苦手、癖のあるお香は苦手、古臭いのも苦手… そんな人にも刺さるだろうし、もちろんお香好きにも刺さるお香だ。
手元に一箱あっても損はしない、オススメの一箱。
落ち着いた気持ち、爽やかな気持ちになりたい時に、薫きたい。